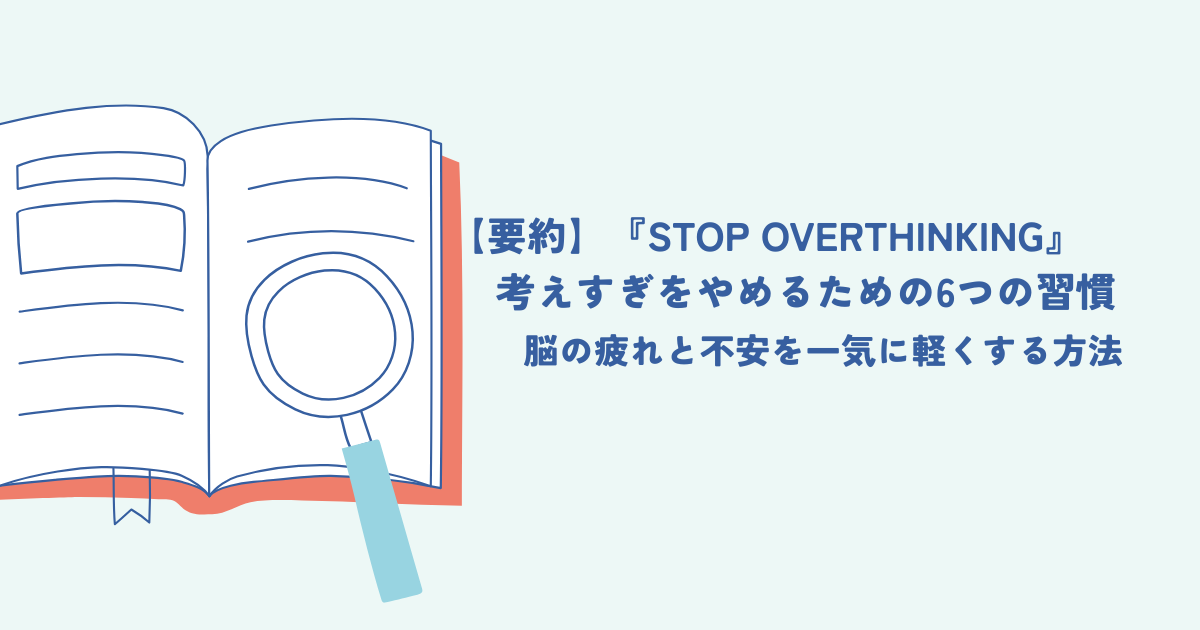現代人の多くが抱える悩み、それが「考えすぎ(オーバーシンキング)」。
SNSの情報、他人との比較、仕事・恋愛・将来の不安…。
一度考え始めると終わりが見えず、脳のスタミナだけが消耗していきます。
今回の記事では、行動心理学の専門家 ニック・トレントン のベストセラー
『STOP OVERTHINKING』の内容を要約し、今日から実践できる「考えすぎを止める6つの習慣」を紹介します。
1. 考えすぎの正体は「遺伝26%」×「環境74%」
著者によると、考えすぎの原因は以下の通り。
- 遺伝:26%
- 環境:74%
特に環境による影響が大きく、たとえば
- 散らかった部屋
- イライラする上司
- 不安定な家庭環境
- 子ども時代から比較されて育った
などは考えすぎを悪化させる主因になります。
ただし、遺伝も環境も変えられない。
だからこそ本書は「考え方・捉え方」を変える方法に焦点を当てています。
【考えすぎをやめる6つの方法】
2-1. コントロールできないことは考えない
古代哲学者エピクテトスの教えでもある「可変と不可変の区別」。
自分で変えられることだけに集中する。
逆に、
- 相手の気持ち
- 過去の出来事
- 結果
- 死や天候
- 他人の評価
これはすべて「自分ではどうにもできない領域」です。
たとえば恋愛で“返信がこない”と悩むのは、完全に相手側の領域。
自分で動かせない岩を押し続けても、疲れるだけ。
まずは
「いま悩んでいること、自分にコントロールできる?」
と質問してみてください。
2-2. 頭のモヤモヤはすべて書き出す(ジャーナリング)
考えすぎると、視野が狭くなり整理ができなくなります。
その状態でいくら悩んでも解決には向かいません。
そこで有効なのが 「ジャーナリング(書き出し)」。
- 感じている不安
- イライラ
- 悲しみ
- 気になること
これを紙やスマホのメモに書くだけでOK。
書くことで
✔ 思考が外に出る
✔ 感情が落ち着く
✔ 何をすべきか冷静に判断できる
ため、うつ症状の軽減にも効果があると研究で証明されています。
2-3. 五感を“今いる場所”に戻す(アーシング)
考えすぎは「意識が未来や不安に向いている状態」。
これを強制的に“今”へ引き戻す方法が アーシング。
- 土や芝生の上を裸足で歩く
- 木や自然に触れる
- 部屋の冷たい机に触れる
- 呼吸に意識を向ける
- 飲み物の味に集中する
こうした「五感を使う行動」は、脳を現在に引き戻してくれるため、不安のループを断ち切る最も簡単な方法です。
2-4. 思考がパンクしているときは、とにかく休む
不安やイライラの多くは、
睡眠不足・疲労・身体の不調
から発生します。
- よく眠る
- 美味しいものを食べる
- 散歩する
- サウナに行く
- SNS・通知から離れる
休息は“おまけ”ではなく、脳の性能を維持するために必須です。
2-5. 言葉で「自分を実況中継」して客観視する
心理学では「ラベリング」と呼ばれる方法。
「今、私は不安を感じている」
「今、イラッとしている自分に気づいている」と声に出す、または心の中で言語化すると、
自分を外側から見る視点が生まれます。
視野が広がることで、
絶望が和らぎ、不安が小さくなるのがこの方法の最大のメリット。
さらに効果的なのが「10年後の視点」
いまの悩みを“10年後にどう感じているか”想像すると、
ほとんどのことが大した問題ではなくなります。
2-6. 重要度×緊急度でタスクを分類する
最後は、頭の中のごちゃごちゃを整理する方法。
重要度 × 緊急度マトリックスでタスクを4つに分類します。
① 重要 × 緊急
→ 最優先で即やること(締め切り・仕事・試験)
② 重要 × 非緊急
→ 将来のために必要なこと(運動・読書・健康診断)
③ 緊急 × 非重要
→ 他人が急に作った用事(突然の電話・不要な買い物)
④ 非緊急 × 非重要
→ SNS・ダラ見・ゲームなど
「悩むべきこと」と「スルーでいいこと」が一瞬で判別できます。
■ まとめ:考えすぎは“思考の習慣”で止められる
最後にもう一度ポイントを整理します。
🔹考えすぎをやめる6つの習慣
- コントロールできないことは考えない
- ジャーナリングで書き出す
- 五感を“今”に戻す
- 休息を最優先
- 言葉で自分を客観視
- 重要度×緊急度で整理する
考えすぎは“才能”でも“性格”でもなく、
脳が疲れている時に起こる習慣の問題です。
今日からできる小さな習慣で、
必ず心は軽くなります。
書籍